人間はもっと「いい加減」に生きるべきである【適菜収】
【連載】厭世的生き方のすすめ! 第10回
■力を抜いた大人になる
私は作家という職業柄、これまで多くの出版社の編集者とお付き合いしてきた。その中でも大きな影響を受けた編集者がいる。私が30歳の頃、川田は50歳だった。あるとき「適菜さん。僕、大事な相談があるので飲みに行きませんか」と電話がかかってきた。それで某駅近くの北海道料理屋に行った。
川田は言う。
「僕、うっかりしちゃったんですよ。雑誌の企画を出すのが間に合わなくて、編集長に叱られたんです。この前もまともな企画を出せていないと言われて、嫌になっちゃった。それで『A』(ライバル誌)の企画を全部盗むことにしたんです。そしたら企画が通って、編集長からやればできるじゃないかとほめられたんです」
私はルイベを食べながら適当に相槌を打った。川田は続ける。
「それで、企画だけではなくて、内容も全部盗もうかなと」
「それはまずいんじゃいですか」と私は答えた。
「そうですよねえ。バレたら編集長に叱られますよねえ」
川田の行動基準は善悪ではなく、すでに「編集長に叱れるか叱られないか」になっていた。川田は胸を張る。
「でも、内容はともかく企画を盗むという一線はきちんと守ろうと思うんです」
そこは守るところではない。
*
翌年、川田から電話がかかってきた。
「適菜さん、実は大事な相談があるんです。僕、会社を辞めようと思っているんです。もう、全部嫌になっちゃった」
「辞めた後はどうするんですか?」
「僕の自宅の前がお寺の参拝路なので、そこで、おでん屋をやろうと思うんです」
「すごいですね」
「でしょう」
「そのお店では、酒も出すんですか?」
「でもね、僕、料理が嫌いなの」
「え?」
「だからお店では、おでんの缶詰を出そうと思って」
その日は忙しかったので電話を切った。
*
川田と知り合って5年くらいたった頃、取材の後、JR中野駅の裏にあった「北国」という居酒屋に行った。古民家風の建物でおばあさんが2人で店を切り盛りしていた。私と川田がそこで酒を飲んでいると、常連客と思われるオッサン3人組が入ってきて、こちらが気になったらしく話しかけてきた。そいつらの態度が悪かったので、無視していたが、「兄ちゃん、齢はいくつなんだ?」としつこい。当時私は30代前半だったが、面倒なので「もう還暦だよ」と答えた。すると、川田がオッサンより先に大きな声を出した。
「へえーっ! びっくりしましたあ。適菜さんってもうそんなお歳だったんですねえ!」
5年間もつきあっていて、コレですよ。
*
あるとき、取材で北海道の旭川に行くことになった。その日は乱気流で飛行機が旭川空港に着陸できず、上空で旋回した後、羽田空港に戻ってきた。ずっと揺られっぱなしで、私は具合が悪くなり、真っ青になっていたが、川田は気持ちよさそうに寝ていた。羽田に着いて目を覚ました川田は到着ロビーに出てしばらくしてから「ここ旭川じゃないですよね」と言った。私を怒らせたいのか?
*
あるとき夜道を歩いていると、川田がいきなり立ち止まった。
「あのう、あのう……」
私は「どうしたんですか?」と聞いた。
「あのう。僕、うさぎの柄のマフラーつけていませんでした?」
「気づきませんでしたが」
「僕のマフラーがないんです」
「落としたんじゃないですか?」
川田は大きな声を出した。
「あっ、そうかあ! ちょっとここで待っていてください」
しばらく暗い道で待たされて川田が戻ってきた。なにも言わなかったが、マフラーはつけていた。私はこんな大人になりたいと思った。
文:適菜収
- 1
- 2


-1-697x1024.jpg)
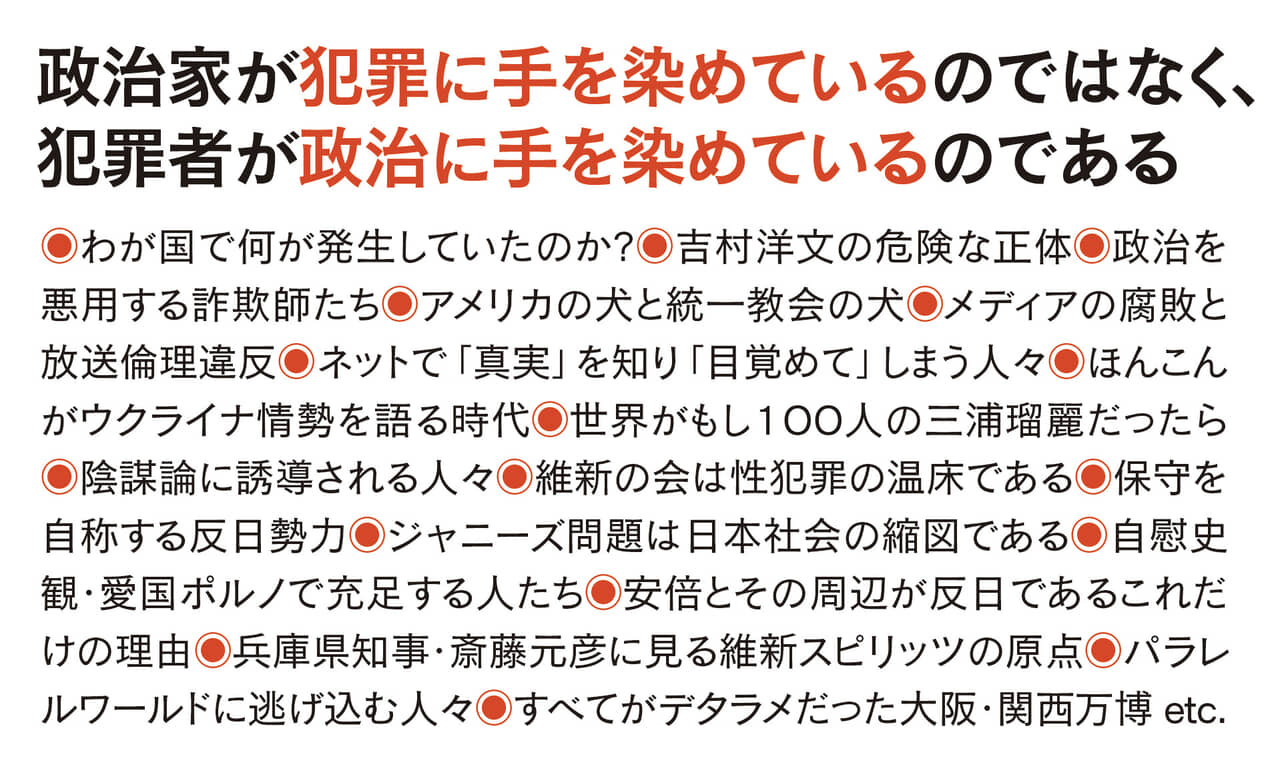
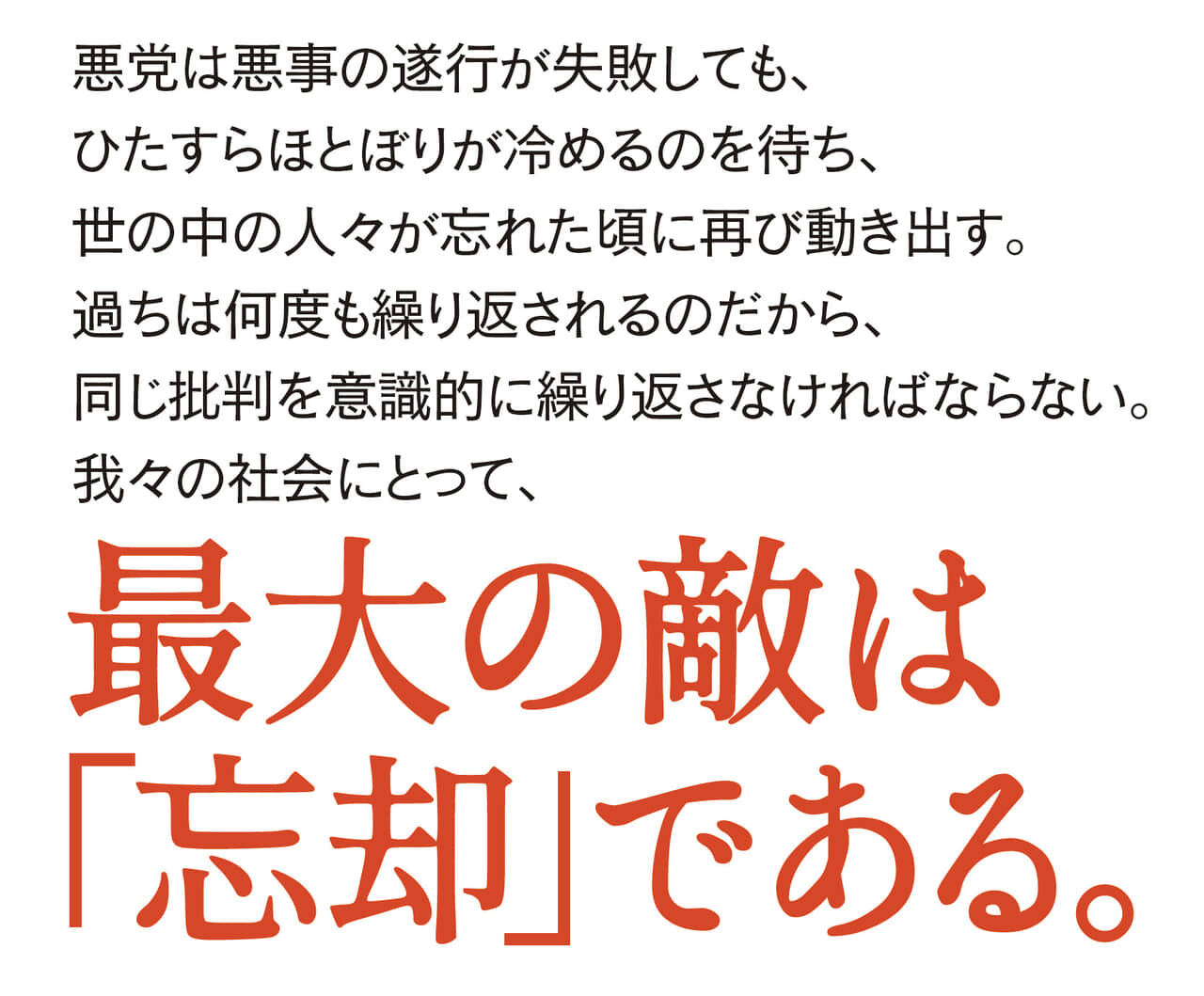
-697x1024.jpg)








